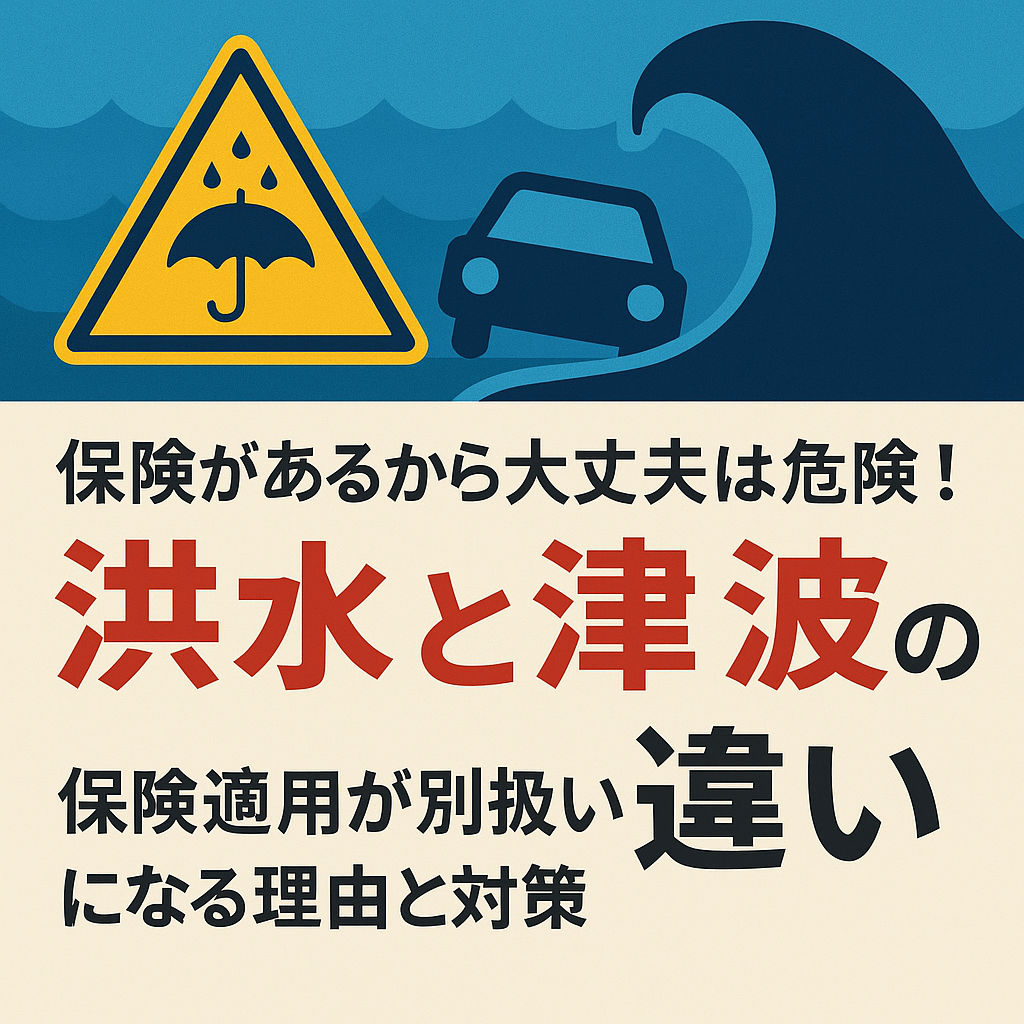
はじめに
夏から秋にかけて、日本列島を襲う台風や集中豪雨。気象庁の統計によると、ここ10年間で「50年に一度の豪雨」が毎年のように発生しています。その影響で道路の冠水や河川の氾濫が頻発し、車が水にのまれる被害が後を絶ちません。「保険があるから大丈夫」と思っている方も多いですが、水害の種類や原因によっては保険が適用されないケースも存在します。
クルマは思った以上に水に弱い
車は精密な電子機器と機械部品の集合体であり、水への耐性は非常に低いです。わずか数十センチの冠水でも、エンジンに水が入り込み、動かなくなることがあります。また、電装系がショートして修理不可能となり、結果的に全損扱いになることも少なくありません。
特に駐車中の浸水被害は深刻です。カーペットやシートが水浸しになるだけでなく、フロア下の制御ユニットや配線が損傷し、見た目では分からない致命的なダメージを受ける場合があります。
洪水と津波、補償はなぜ違う?
洪水と津波、どちらも「大量の水」による被害ですが、自動車保険では全く異なる災害区分として扱われます。
- 洪水: 台風、豪雨、融雪などの気象現象によって発生。河川の氾濫や土砂崩れも含まれる。
- 津波: 地震や海底地殻変動が原因で発生。水害ではなく地震災害の一種として扱われる。
多くの自動車保険では、洪水による車両の損害は車両保険で補償されますが、津波による損害は「地震・噴火・津波による損害」として免責、つまり補償対象外とされています。これは火災保険や家財保険でも同様です。
自然災害下での運転と保険適用の落とし穴
保険契約には「危険を予見しながら敢えて行動した場合」に補償が制限される可能性があります。たとえば、大雨で視界がほぼゼロの中、警報が発令されているにもかかわらず運転を続け、冠水路に突入した場合などです。
保険会社は「危険回避可能だった」と判断すれば支払いを拒否することもあります。特に近年のゲリラ豪雨や線状降水帯は短時間で道路を冠水させるため、外出を控える判断も重要です。
水没車はこうして流通する
車が水没すると、多くの場合は修理不可能として保険会社が全損扱いとします。その後、水没車は解体されるか、海外や国内の一部市場に流れます。しかし一部では、不正に再販売されるケースも存在します。
あまりにも安い中古車には注意が必要です。水没歴が隠されている可能性があり、購入後に電装系の不具合や錆の進行が発覚することも。中古車は信頼できる業者や公的な履歴情報が確認できるところから購入しましょう。
予防と備え
- 大雨や台風接近時は安全な高台に駐車する
- 河川沿いや低地での駐車を避ける
- 天気予報や警報情報をこまめにチェック
- 車両保険の補償範囲を確認し、必要に応じて地震保険や特約を追加
まとめ
洪水と津波、どちらも水害に見えますが、保険適用の仕組みは大きく異なります。水害は補償されても、津波は対象外というケースがほとんどです。また、危険が予見できる状況での運転は補償が制限される可能性もあります。
近年はゲリラ豪雨や線状降水帯による冠水被害が増加しており、水没車の流通リスクも現実的な脅威です。愛車を守るため、そして不要なトラブルを避けるためにも、保険内容の確認と日常的な予防行動を欠かさないようにしましょう。
