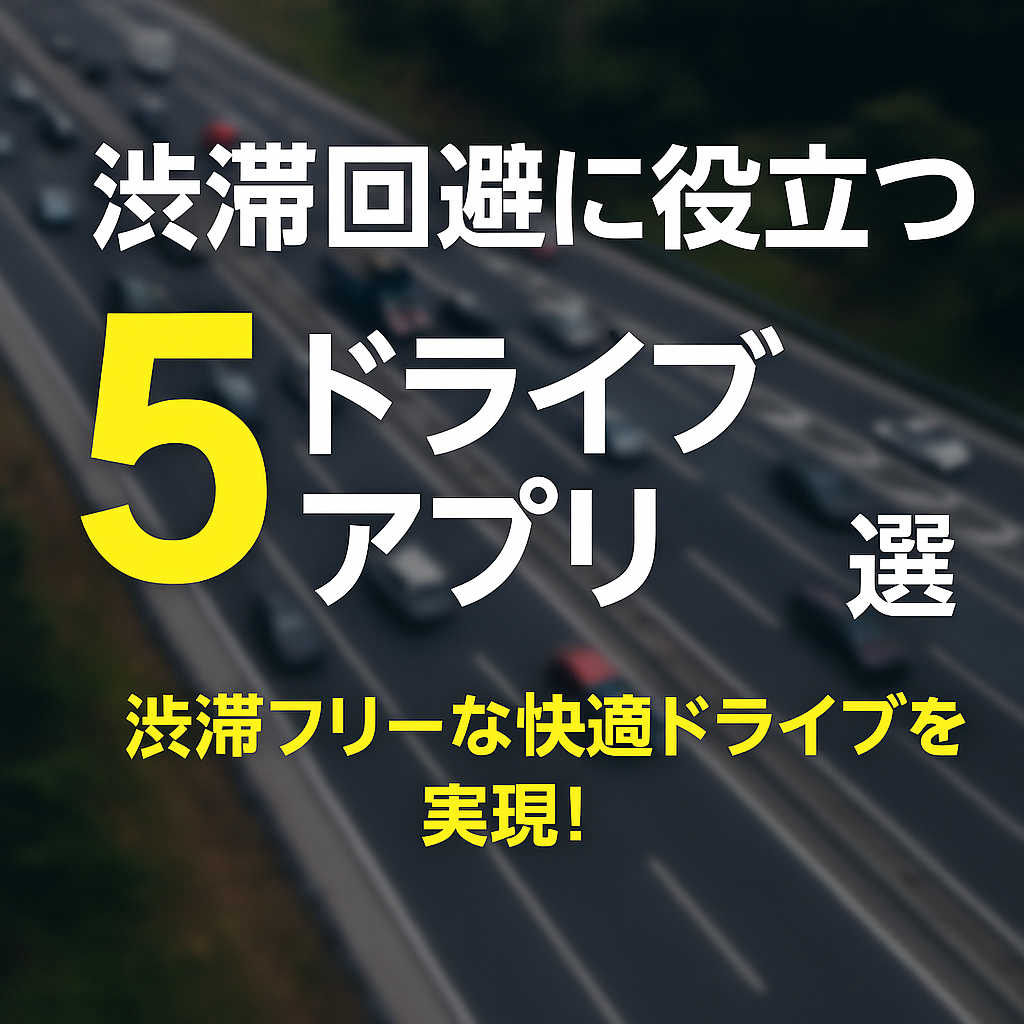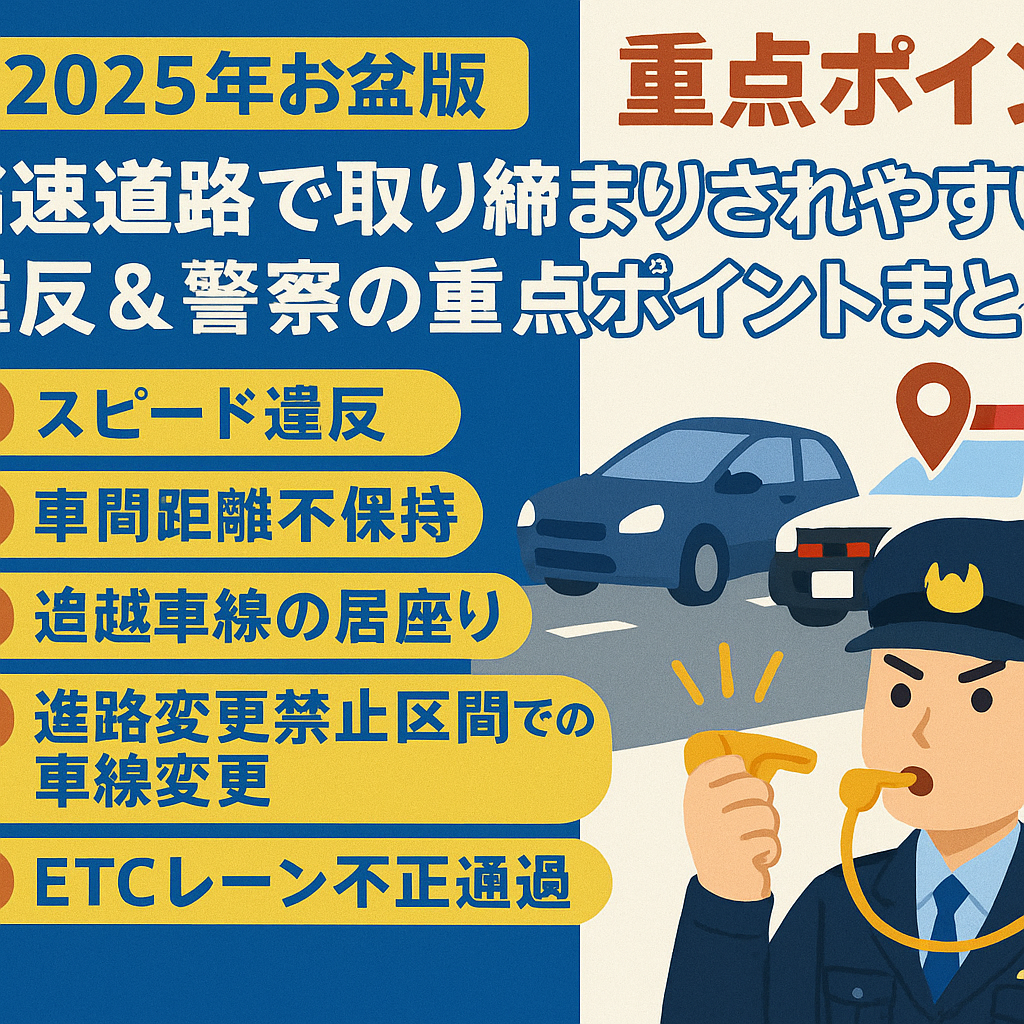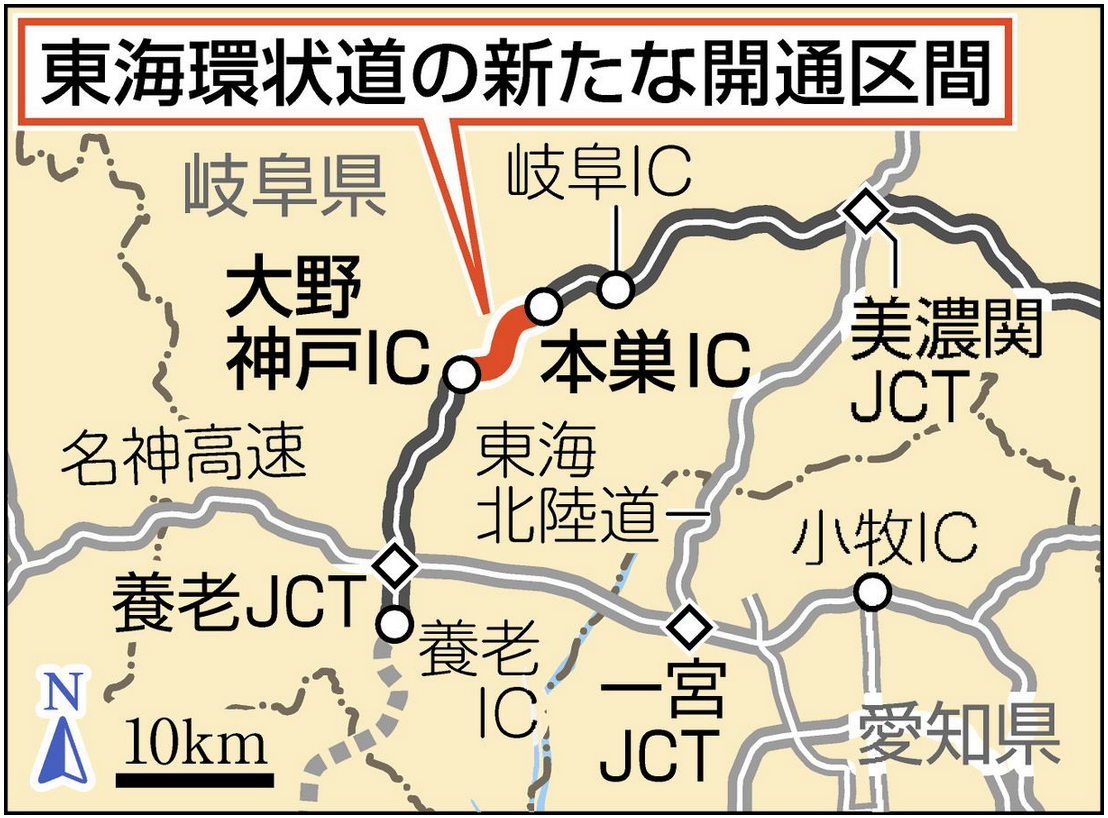お盆の帰省やドライブの途中、有料道路の料金所に「ETCGO」と書かれたレーンを見つけました。普段は楽天のETCカードを使っている私ですが、そのときは非対応だったようでゲートが開かず、仕方なく別の方法で料金を支払いました。少し戸惑いながらも「そもそもETCGOって何?」と気になり、調べてみることにしました。
ETCGOは“多目的ETC”だった
調べてみて分かったのは、ETCGOは高速道路だけに限らず、駐車場や観光道路、さらにはドライブスルーなどでも利用できるキャッシュレスサービスだということ。これまでのETCが“ノンストップ通行”を前提にしているのに対し、ETCGOは一旦停止してから決済する方式を採用しています。
その分アンテナや機器を簡素化でき、導入コストが大幅に下がるのが特徴だそうです。
通常のETCとの大きな違い
- 車から降りずに支払える点は同じ
- ノンストップではなく、一旦停止してから決済する
- 利用登録は不要で、対応ETCカードを挿入しておくだけ
- クラウド処理により導入コストを抑えられる
こうして比べてみると、ETCGOは「止まるETC」という表現がしっくりきます。都市部の高速道路では渋滞につながるかもしれませんが、小規模の有料道路や駐車場ではむしろ現実的な仕組みといえそうです。
最大の課題は「対応カードの少なさ」
私が利用している楽天カードのETCは非対応でしたが、それもそのはず。公式サイトによると、現時点で使えるのは以下のカード会社のみでした。
- 三井住友トラストクラブ(ダイナース)
- イオン銀行のイオンETC専用カード
- 三菱UFJニコス(MUFG/NICOSの一部)
- トヨタファイナンス
かなり限定的で、普及にはまだまだ時間がかかりそうです。せっかく便利な仕組みなのに、対応カードを持っていないと使えないのは大きなハードルですね。
実際の導入事例
ETCGOはすでにいくつかの有料道路や駐車場で導入されています。地方の観光道路や都市部の駐車場などで稼働しており、徐々にエリアを拡大しているようです。
個人的には、ドライブ旅行の際に立ち寄る観光地の駐車場で使えるようになると便利だろうなと感じました。財布を出す手間がなく、車に乗ったままサッと精算できるのは大きな魅力です。
よく似た「ETCX」との違い
調べている中で「ETCX」という名前も見かけました。こちらは別会社が運営しており、事前の会員登録が必要です。仕組みはETCGOと似ていて、どちらも停止前提の決済システム。
つまり現在はETCカードを使った派生サービスが2つ並立している状況で、利用するにはロゴや案内表示を確認する必要があるということです。
実際に体験して感じたこと
私はETCGOに遭遇して初めて「ETCにも派生規格がある」ということを知りました。最初は少し戸惑いましたが、調べてみると意外と合理的な仕組みで、駐車場や小規模道路に向いていると納得しました。
今後カード対応が広がれば、ドライブの自由度が高まりそうですし、観光やレジャーのときにもっと活躍するかもしれません。
まとめ
ETCGOは「止まって決済する多目的ETC」といえるサービスでした。高速道路のようなスピード感はないものの、導入コストを抑えつつ幅広いシーンで使える点が魅力的です。
現状では対応カードが限られているため、利用予定がある方は事前に対応一覧を確認するのがおすすめです。今後の普及に期待したいと思います。