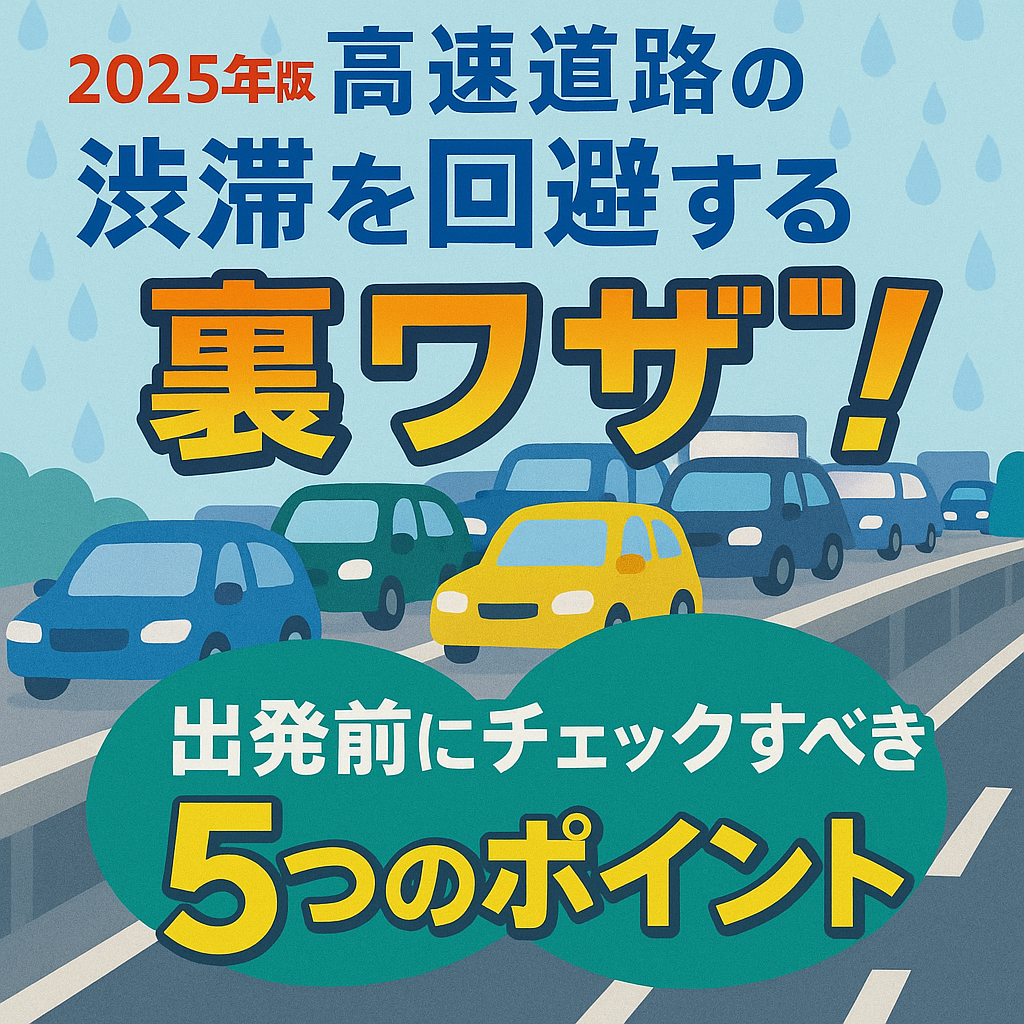【実体験】現金払いが当たり前だった高速道路の時代──料金所の混雑、驚きの裏技、そして「40万円の貯金」
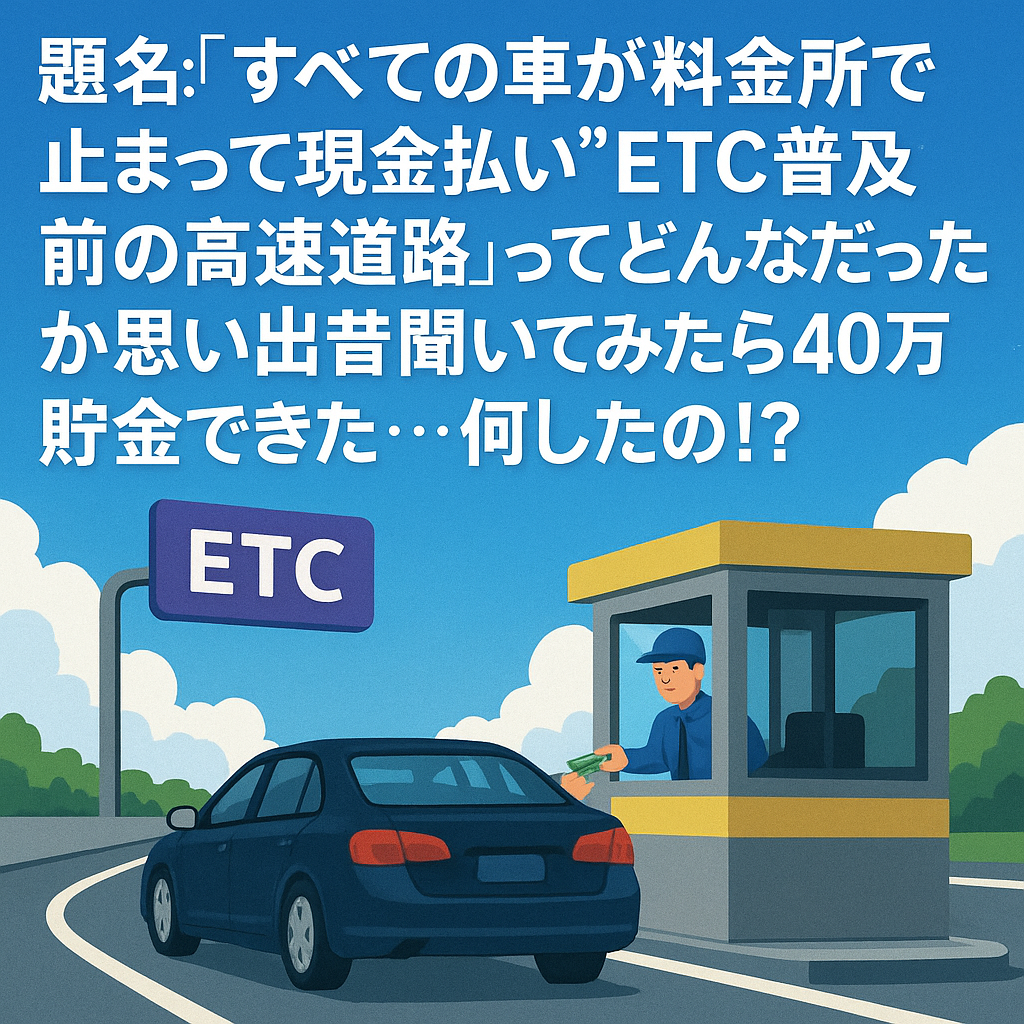
2025年4月、NEXCO中日本のETCシステムに大規模なトラブルが発生し、料金所での混乱や渋滞がニュースになりました。これを見て、私はふと「ETCが普及する前の高速道路の風景」を思い出したのです。
いまでは考えられないかもしれませんが、すべての車が料金所で止まり、運転席から現金を差し出すのが当たり前の時代がありました。当時の体験を振り返りながら、その不便さ、工夫、そして意外な“お得体験”についてご紹介します。
1. 高速道路は渋滞の宝庫だった
私は1990年代から長年、週末ドライバーとして関東近郊をあちこち走ってきました。当時はETCなんて影も形もなく、インター入口でチケットを受け取り、出口で料金を現金精算。これが“当たり前”の風景でした。
特に記憶に残っているのは、中央道・八王子料金所の大渋滞。連休になるとインター出口から本線に向かって数kmにわたって車が連なり、「降り口にたどり着くまで1時間以上かかった」なんてザラでした。
2. トイレ渋滞との闘い
家族旅行では「トイレ問題」が深刻でした。ある日、仙台方面へ向かっていた時、パーキングをスルーしてしまい、直後に大渋滞に巻き込まれました。後部座席で彼女が「もう我慢できない!」と泣き出して大変だった記憶があります。
当時はリアルタイムの渋滞情報もほとんどなく、「突然渋滞にハマる」ことが日常茶飯事でした。今のように渋滞回避のナビやアプリがある時代が、いかに恵まれているか、実感せずにはいられません。
3. 環状族と“料金所スルー”の衝撃
大阪に転勤していた頃、阪神高速の“環状族”をよく見かけました。彼らは改造車で爆音を響かせ、料金所をノンストップで突破していくのです。バーが設置されていない頃は、料金所の役割が果たされていないような状況でした。
警備員がいてもナンバープレートを隠されていれば、どうにもならず。あれが“高速道路の現実”だった時代は、今では信じられない話でしょう。
4. コインホルダーのありがたさ
現金精算時代に役立ったのが、車に備え付けの「コインホルダー」でした。100円玉や50円玉を仕分けておき、料金所でスマートに支払えるように準備していました。
中には「デートの前にお札を崩して準備していた」という人も少なくなかったでしょう。コインホルダーがガチャガチャとうるさかった思い出も含めて、今となっては懐かしいです。
5. 40万円が貯まった「お釣り貯金」
私は、高速を使うたびに「必ずお札で払う」というルールを自分に課していました。理由は簡単、余った小銭を“そのまま貯金箱へ”放り込むためです。
当時は毎週2〜3回、高速を使っていたので、小銭はどんどん貯まっていきました。10年間で約40万円にもなったこの方法、今ではETCで支払いが自動化されたため、実現不可能ですが、あの頃の“お釣り貯金”には小さな楽しみがありました。
6. ETCの登場と料金所革命
2000年代に入ってETCが登場したとき、「これで料金所のストレスから解放される!」と喜んだのを今でも覚えています。初期はETC搭載車も少なく、私はいち早く導入して、友人に「ETCいいぞ!」と勧めて回っていました。
国土交通省によれば、ETCの利用率が2003年には6.1%だったのが、2007年には73%に上昇。料金所の渋滞は95%も減ったそうです。それほどまでにETCはドライバーにとって革命的なシステムでした。
7. 便利さと引き換えに失ったものも
もちろん、ETCによって快適になった反面、失ったものもあると感じます。例えば、料金所での一言二言のやり取り。顔なじみの徴収員さんがいたり、「お釣りちょうだいね」と笑い合ったり──ああいう人とのつながりが、少しずつ消えていったような気がします。
まとめ|あの時代があったから、今の快適がある
今回のETCトラブルを機に、改めて「現金精算が当たり前だった時代」の高速道路を思い返しました。
あの不便さと、それを乗り越える工夫、そして小さな幸せ──それらの積み重ねが、今の快適なドライブを作っているのです。これからの未来もまた、新たな技術と共に進化していくでしょうが、時にはこんな「過去を懐かしむ時間」も大切なのではないでしょうか。