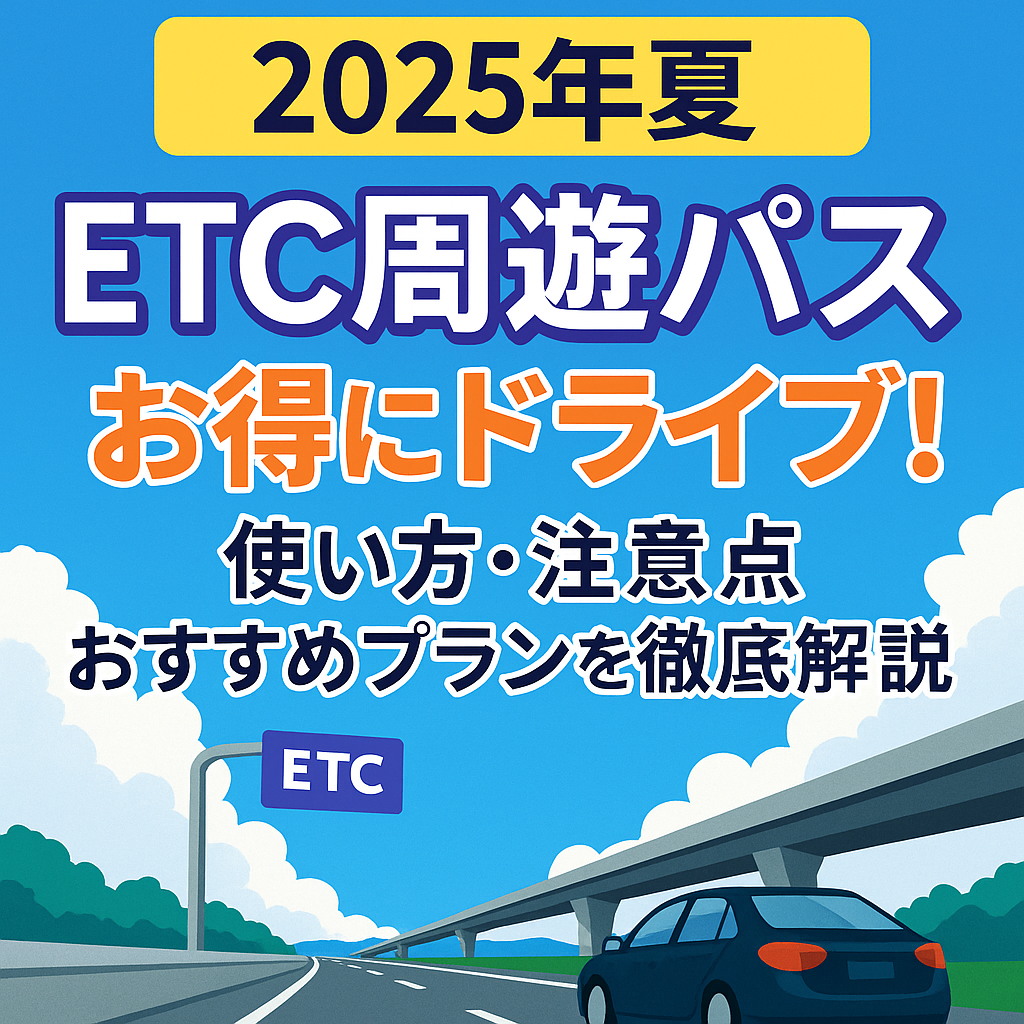ETCが使えなくなる!?『2030年問題』とは|背景・影響・対策を徹底解説

はじめに:突然やってくる“ETCの終わり”
今やほとんどの車が装着しているETC(Electronic Toll Collection)。料金所をスムーズに通過できる利便性から、高速道路利用者には欠かせない存在となっています。しかし近年、このETCに関して「2030年には使えなくなるかもしれない」という“ETC 2030年問題”が注目されています。
本記事では、この問題の背景や影響、そして今後の対策について、わかりやすく解説していきます。
1. ETC 2030年問題とは?
「ETC 2030年問題」とは、現在主流となっているETC車載器(特に旧式のETC)およびETCシステムが、2030年頃をめどに使用できなくなる恐れがあるという問題です。
これは単なる「買い替えのタイミング」ではなく、次のような技術的・制度的な背景によって引き起こされます。
2. 背景:なぜ2030年に使えなくなるのか?
2-1. セキュリティの問題
ETCは無線通信により料金所と車載器の間でやりとりを行っていますが、現在のETC(ETC1.0)では通信暗号の強度が弱く、今後のサイバーセキュリティ要件に対応できないという問題があります。
政府・高速道路会社はこれを重く見ており、2030年までに新しい暗号化方式を備えたETC2.0へ完全移行する計画を進めています。
2-2. ETCシステムの更新と互換性の終了
現在のETCインフラは2001年の運用開始以来、20年以上が経過しています。システム全体の老朽化に加えて、新しいシステム(ETC2.0)に完全移行するタイミングで、古いETC車載器のサポートを打ち切る方針があるとされています。
2-3. ETCの認証サーバーの更新
ETC車載器と料金所ゲートは、相互に「認証」するための証明書(セキュリティキー)を使っています。これらの証明書には有効期限があり、2030年ごろに一斉に期限切れを迎えるため、更新を受けられない古い車載器は使えなくなる可能性があるのです。
3. ETC2.0との違いと対応状況
3-1. ETC2.0とは?
ETC2.0は、従来のETCに加えて以下のような高度な情報提供機能を持つ進化型のシステムです。
-
渋滞・事故情報のリアルタイム提供
-
一時退出後の再進入でも料金継続(スマートIC対応)
-
今後の自動運転インフラとの連携を見据えた設計
3-2. ETC2.0の普及率は?
国土交通省の発表によると、2024年時点でのETC2.0車載器の普及率はわずか20%未満にとどまっており、ほとんどの車は依然としてETC1.0を使用しています。
このままでは2030年のシステム切り替え時に多くの車がETC非対応になってしまう恐れがあります。
4. ETC 2030年問題の影響
4-1. ETCが使えなくなるとどうなる?
ETC車載器が対応していないと、以下のようなデメリットが生じます。
-
料金所で一般レーンに並ぶ必要がある(時間ロス・渋滞)
-
ETC割引が一切使えなくなる
-
料金所での支払いが現金またはクレカに限定
-
高速道路マイレージなどのサービス対象外
4-2. カーナビ連動・テレマティクスサービスにも影響
ETC2.0は車両データを取得・分析するため、ナビ連動のドライブ支援サービスなどにも影響します。対応車載器を持たない車は、これらの機能が使えなくなる可能性があります。
5. 今後どうすればいい?ドライバーが取るべき対策
5-1. 2030年までにETC2.0への買い替えを検討
現在ETC1.0を使用している方は、2030年までにETC2.0対応の車載器に買い替える必要があります。買い替え時には以下のポイントに注意してください。
-
セットアップが必要(車両情報を登録)
-
補助金制度を活用できる場合あり(次項参照)
-
ナビとの連動機能の確認も推奨
5-2. 補助金制度を活用しよう
過去にはETC2.0導入にあたり国土交通省やNEXCOが補助金制度を実施していました。今後、2030年問題に向けた支援策が再び実施される可能性がありますので、チェックしておくとよいでしょう。
6. なぜ今のうちに知っておくべきか?
2030年までまだ数年あると思われがちですが、次のような理由から早期の情報収集と対策が求められます。
-
補助金には予算・期間の制限がある
-
ディーラーやカー用品店の予約が混雑する可能性
-
中古車購入時に非対応車載器を選んでしまうリスク
また、直前に大量の買い替えが集中すると、設置業者の予約が取りづらくなる事態も予想されます。特に長距離ドライバーや業務用車両では深刻な影響が出るため、早めの準備が重要です。
7. Q&A|よくある疑問に回答
Q:ETC1.0が2030年以降も使える車載器はあるの?
A:一部の車載器では、2030年以降も継続利用が可能な設計になっている可能性がありますが、保証はされていません。認証の更新に対応していない機種は使えなくなるため、メーカー確認が必要です。
Q:2030年までは今のETCを使い続けていいの?
A:はい、現在のところ2030年まではETC1.0でも問題なく利用できます。ただし、先に説明したように、セキュリティや制度変更によって前倒しで使えなくなるケースもあります。
Q:買い替え費用はいくらくらい?
A:ETC2.0の車載器本体は約15,000〜25,000円、工賃・セットアップ込みで20,000〜30,000円前後が目安です。補助金が出る場合はこれより安く済むこともあります。
おわりに:今のうちに“2030年問題”へ備えよう
ETC 2030年問題は、単なる車載器の更新ではなく、高速道路利用に関わる大きな転換点です。ギリギリまで放置してしまうと、割引が使えなくなったり、通行に支障が出たりと不便なことが多くなります。
2025年の今だからこそ、こうした情報を把握し、余裕を持って対策を講じることが重要です。今後の制度動向や補助金情報にも注目しながら、自分に合ったタイミングでETC2.0への移行を検討してみてください。