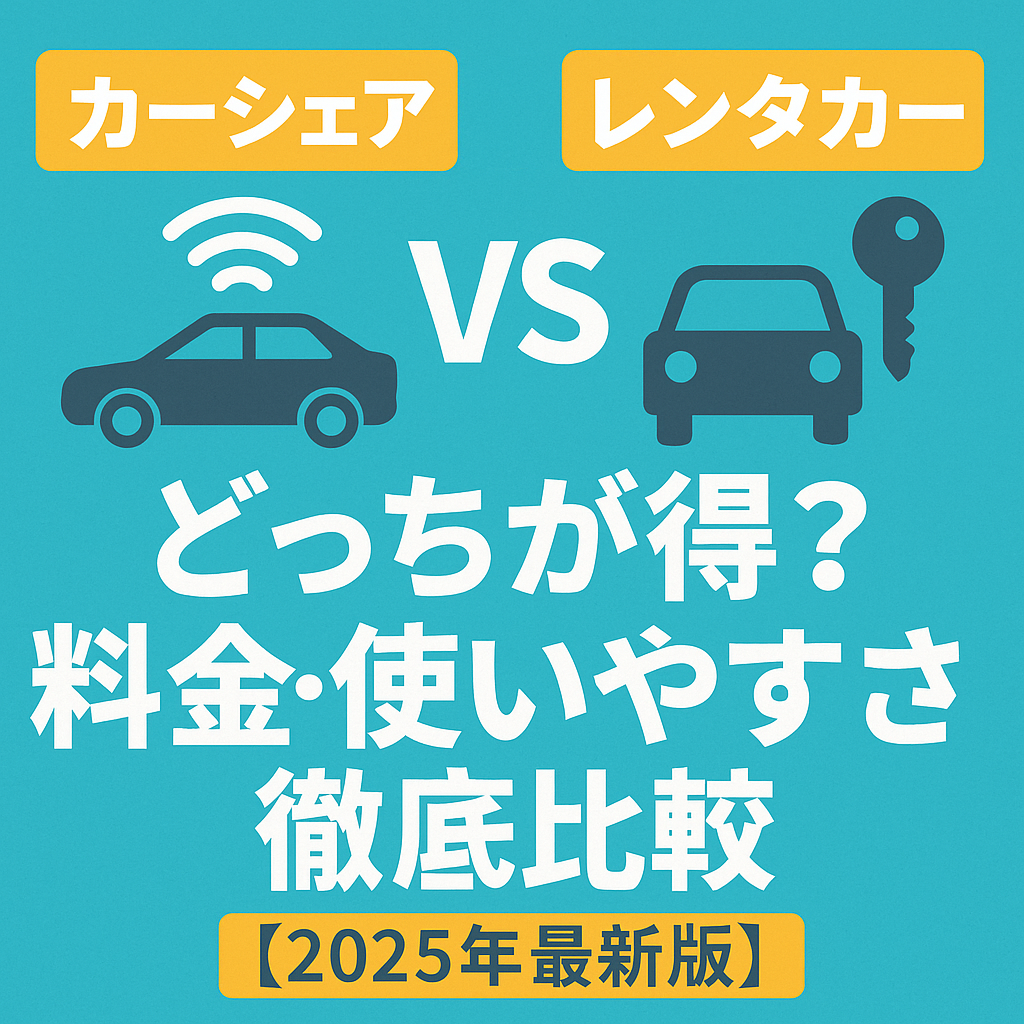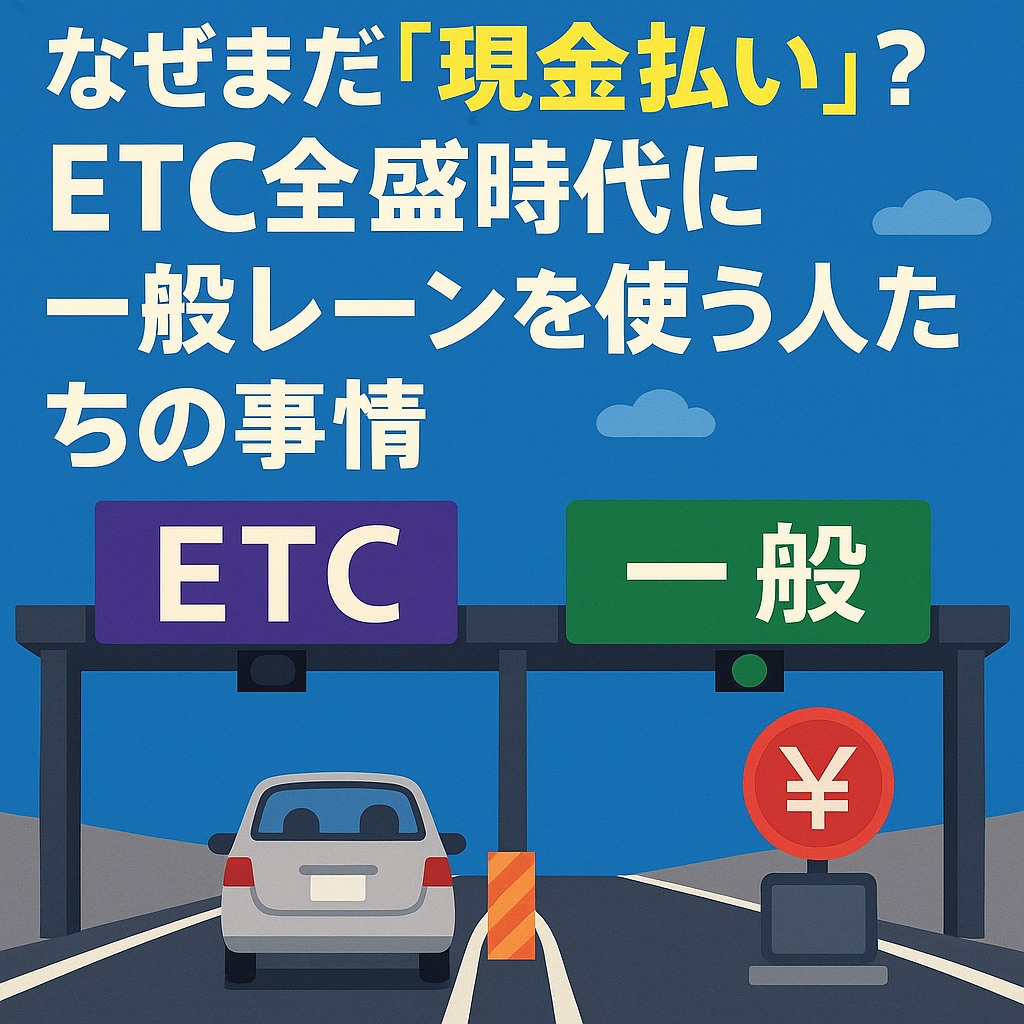
ETC時代でも現金払い?高速料金所で「一般レーン」を選ぶ人たちのワケ
ほとんどがETCなのに、なぜ一般レーンがなくならない?
いまや高速道路の料金所で見る車のほとんどが、紫色の「ETC専用レーン」をスムーズに通過していきます。
それでも、現金払い用の緑色の「一般」レーンには必ず数台の車が並んでいる――そんな光景を見たことはありませんか?
ETCがこれだけ普及しても、あえて一般レーンを利用するドライバーが存在する理由を探ってみました。
ETCの歴史と現在の普及率
ETCの全国導入は2001年12月。
2007年3月の時点で利用率は65.9%(525万台)、2016年には90%を突破し、2025年5月現在では利用率95.3%・台数828万台にまで増加しています。
かつては料金所で窓を開けて通行券を受け取り、帰りに料金所で現金払いするのが普通でした。
しかし今や、現金払いは少数派になっています。
一般レーンを使う主な理由
1. 車載器やセットアップ費用を払いたくない
ETC車載器はネットや量販店で買えますが、セットアップは登録業者でしかできず、費用は3,000〜4,000円前後かかります。
DIY好きな人ほど「なぜ自分でできないのか」と不満を持ち、導入を避けるケースがあります。
2. 高速道路の利用頻度が低い
年に数回しか高速を利用しない人にとっては、ETC車載器やカードの導入コストがもったいないと感じられます。
3. ETCカードが作れない
ETCカードはクレジットカードとセットで作るのが一般的ですが、過去の延滞や自己破産などでカードを発行できない人もいます。
特にスマホの分割払いの延滞は、将来のローンやカード発行に大きく響くため注意が必要です。
4. 車の外観や時代感を守りたい旧車オーナー
2001年以前の車にはETCが標準でなく、旧車やネオクラシックカーのオーナーは「当時感」を保つためにあえて付けない場合もあります。
見た目を損ねたくない、というこだわりです。
まとめ:背景を知れば見え方が変わる
ETCは便利で効率的ですが、全員が使えるわけではなく、使わない選択をする人にも明確な理由があります。
次に料金所で一般レーンに並ぶ車を見たら、「事情があるのかもしれない」と思えるかもしれません。