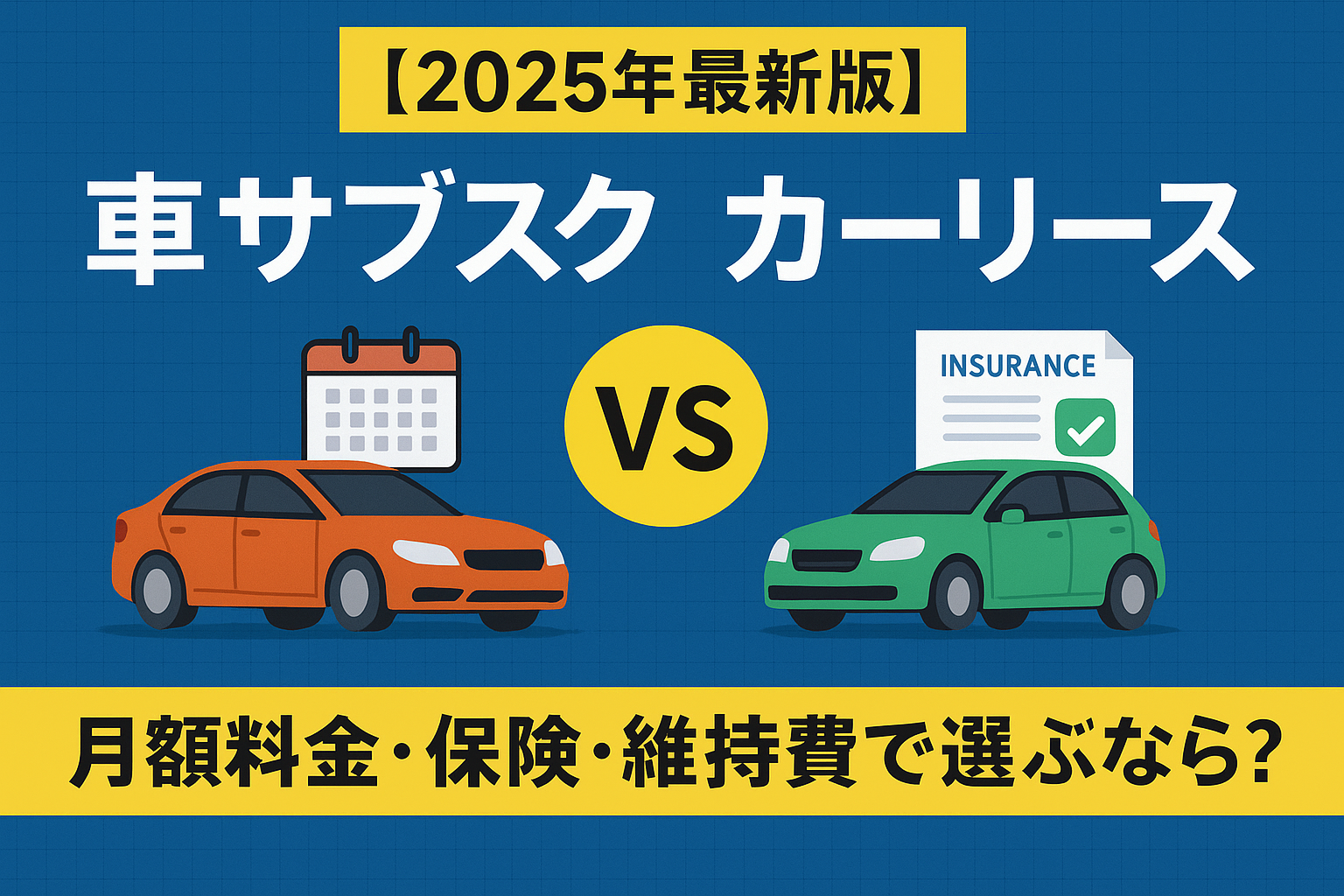ガソリン暫定税率は11/1廃止へ。でも軽油は据え置き?価格差ほぼ5円の理由とこれから
まず結論:ガソリンは下がる、軽油はそのまま
臨時国会(8月1日開会)で提出された「ガソリン暫定税率廃止法案」が成立すれば、11月1日からガソリンは1Lあたり25.1円値下げ。一方、物流の主役であるトラックが使う軽油の「軽油引取税」暫定分(17.1円)は対象外です。ここが今回の最大の“ひっかかり”。
軽油が外れたワケ:地方税ゆえの壁
軽油引取税は地方税。本則15円+暫定17.1円=合計32.1円/ℓが課税されています。暫定は90年代初頭の道路財源確保が出自で、「暫定」の名を保ったまま実質恒久化。
この暫定を外すと自治体歳入は年約5,000億円の減とされ、道路維持や地域交通の補助などに直撃します。今回、与野党ともに自治体の強い反発を踏まえ、まずはガソリンのみを動かし、軽油は見送った――というのが実相です。
数字で見るインパクト:差額は約20円 → 約4円80銭
7月28日時点の全国平均をベースに試算すると、
・レギュラー:174.0円 → 158.9円(25.1円下落)
・軽油:154.1円(据え置き)
結果、ガソリンと軽油の差は約20円 → 約4円80銭に。
「軽油=ぐっと安い」という感覚は大きく薄れ、ディーゼル乗り(乗用・商用とも)には心理的な逆風。経営の厳しい中小運送業者には「恩恵ゼロ」の印象が残ります。
各サイドの主張:誰が何を言っているか
- 物流・業界団体:日本トラック協会は一貫して暫定の撤廃を要望。「物流の99%はトラック。軽油負担の軽減=物価対策」と訴求。
- 野党・与野党議員:維新は二段階減税を提案(まずガソリン、2026年度から軽油)。国民民主・玉木氏は「ガソリンとセットで見直すべき」とSNSで主張。
- 自治体:「5,000億円の減収は道路・交通・生活インフラに直撃。代替財源なき廃止は困難」と強い警戒感。
歴史の復習:なぜ“暫定”が長生きしているのか
暫定税率は景気後退と財源不足への“つなぎ”として導入。2009年に道路特定財源が一般財源化されても、税の骨格は温存され「名ばかり暫定」に。今回の議論は、「何に、どれだけ、誰が負担するか」という財政の原点回帰を迫っています。
家計・事業者への影響:誰が得して、誰が取り残される?
ガソリン車ユーザー:即効性のある恩恵。通勤・行楽の心理的ハードルが下がる。
ディーゼル乗り(乗用):ガソリンとの価格差縮小で、燃料優位性の訴求が難しく。
運送業:軽油据え置きで直接的な原価は変わらず。運賃転嫁が難しい中小は引き続き厳しい。
自治体:ひとまず収入は維持。ただし将来の見直し議論には常時さらされる。
これからの論点:代替財源と設計のやり直し
- 代替財源をどう組むか:燃料課税の割合を見直す?一般財源で穴埋め?環境課税や走行距離課金の是非?
- 段階的減税の道筋:「まずガソリン、次に軽油」という政治的着地点は現実的か。
- 価格転嫁と物価:物流燃料が据え置きだと、物価面の効果は限定的になりうる。
まとめ:値下げは見える化、課題はこれから
11月のガソリン値下げは確定的な朗報。ただ、軽油据え置きにより物流・ディーゼルユーザーのモヤモヤは残ります。価格差が約5円まで縮むインパクトは小さくありません。
政治は「自治体財政」「物価と物流」「利用者の納得」の三点を同時に満たす新ルール作りに踏み込めるか。注視していきましょう。